理科の中でも物理、特に力学分野は、
実験を行うのがとても難しい分野です。
一見簡単そうに見える「てこ実験器」も、
隠された工夫が随所にしてありますし、
「滑車」などに至っては、滑車や糸の重さで
なかなかつり合わせることができません。
ざっくりとした傾向を見るだけの実験なら可能なのですが、
データをとって比例・反比例などの規則性を見つけようとすると、
装置自体の重さや摩擦に悩まされるのです。
「物体の運動」の単元も例外ではなく、
始めはなかなか理論値通りのデータが出せなくて苦労しました。
しかし最近ようやく良好な実験データを得られるようになってきました。
斜面を球を転がして、
転がす高さと速度の関係を読みとります。


実験作業自体はとても楽しく、
コロコロと転がる球に、特に男の子が大興奮します。
本能的なものを感じます。

速度をはかったり、
机から飛ばして飛距離を調べたり、
木にぶつけてしょうげきの大きさを調べたりと、
何十回もデータとりを重ねてグラフをつくります。
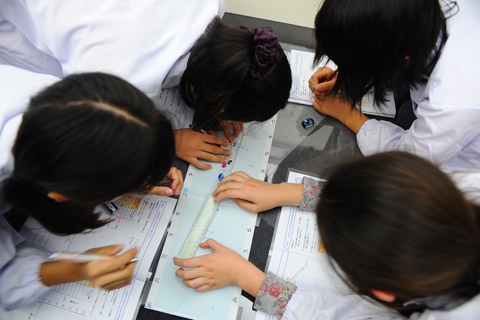
得られるのは物理法則に基づいた、
非常に美しい実験結果です。
といっても、この美しさを感じることができるのは、
普段から数を扱う練習を重ね、数値に対する感性が磨かれている
中学受験生だからこそでしょう。
普通の小学生ではまず不可能です。
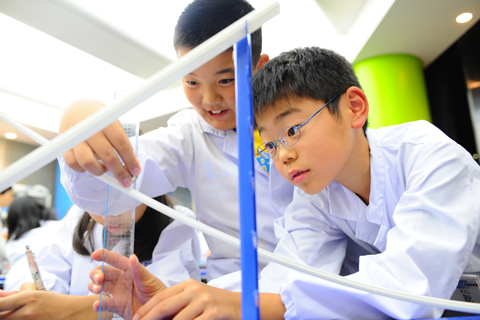
スタンダードコース「運動とエネルギー」より
|

